もう一花咲かせますか! ― 2010年09月18日
カメラも好きで、何気ない風景を撮るのが好きです。
20年位前は、奥日光や八ヶ岳に風景写真を撮りに行っていたものです。
時は過ぎ今やデジカメの時代。あの頃はフィルムの時代。今や画像は電子データで見る時代・・・
でも、おじさんはこれまでのデジ一眼には手が出ませんでした。何かが違う。画像の精細さはデジタルの方が上でしょう。結局フィルムでもスキャナで読み取ってデジタル化しなければならないでしょう。色補正などのレタッチも容易ですから、フィルムメーカーの個性も差が出なくなるでしょう。わかっているんです。
でも、重いレンズ、バシャッと切れるシャッター、一枚づつ巻き上げるフィルム、液晶モニタではなくファインダーから見る被写体。マニュアルでフォーカスや絞りを合わせる作業など、今のデジカメが置いてきてしまったものを、このオヤジは忘れられないのです。
そして、ずっとその画角が忘れられなかった。Mamiya M645 SUPERと35mmレンズとの組み合わせ。35mm換算で約21mmの広角レンズ。寄って撮るということを教えてくれたレンズ。
そして、6×6、6×7に通じる中判カメラだからこその、空気感すらも写し込むような落ち着いた高級感のある画質。マミヤセコールレンズの性能の良さ・・・やっぱ、良いものは良いのです!

スキャナも良いのが出ているようだし、復活させちゃおうかな・・・
これにネオパン400入れて、街撮りしたいなぁ~
フィルムの方が丁寧に撮れるように思います。本当に感覚だけど、フィルムの方が奥行き感はあるように思っていますし、目に優しい?色や光の階調・・・それもあって、デジ一眼には手が出なかった・・・
20年位前は、奥日光や八ヶ岳に風景写真を撮りに行っていたものです。
時は過ぎ今やデジカメの時代。あの頃はフィルムの時代。今や画像は電子データで見る時代・・・
でも、おじさんはこれまでのデジ一眼には手が出ませんでした。何かが違う。画像の精細さはデジタルの方が上でしょう。結局フィルムでもスキャナで読み取ってデジタル化しなければならないでしょう。色補正などのレタッチも容易ですから、フィルムメーカーの個性も差が出なくなるでしょう。わかっているんです。
でも、重いレンズ、バシャッと切れるシャッター、一枚づつ巻き上げるフィルム、液晶モニタではなくファインダーから見る被写体。マニュアルでフォーカスや絞りを合わせる作業など、今のデジカメが置いてきてしまったものを、このオヤジは忘れられないのです。
そして、ずっとその画角が忘れられなかった。Mamiya M645 SUPERと35mmレンズとの組み合わせ。35mm換算で約21mmの広角レンズ。寄って撮るということを教えてくれたレンズ。
そして、6×6、6×7に通じる中判カメラだからこその、空気感すらも写し込むような落ち着いた高級感のある画質。マミヤセコールレンズの性能の良さ・・・やっぱ、良いものは良いのです!

スキャナも良いのが出ているようだし、復活させちゃおうかな・・・
これにネオパン400入れて、街撮りしたいなぁ~
フィルムの方が丁寧に撮れるように思います。本当に感覚だけど、フィルムの方が奥行き感はあるように思っていますし、目に優しい?色や光の階調・・・それもあって、デジ一眼には手が出なかった・・・
懐かしい写真集 ― 2010年08月23日
もう、20年近く前に買ったはずの写真集が見たくなって、家中を探しました。結局無かったのですが、「友人にプレゼントしてしまったかもしれないなぁ~」とあやふやな記憶を手繰ってみたものの、確信があるような無いような・・・結局無かったのだから仕方ない・・・「酋長の系譜」という写真集なんですがね。
でも、懐かしい写真集が出てきました。
まだ、銀塩写真全盛の時代、カメラに夢中になっていた時期がありました。中判カメラを持ち風景写真に没頭していた頃ですね。
その頃購入した2冊の写真集。嶋田忠の「カワセミ」「炎のカムイ」どちらもカワセミ科の鳥の写真集です。嶋田忠は鳥を中心に被写体にした写真家で、NHKでも映像制作したものがあったと記憶しています。
この人の写真集は、動きがあるのと、色や光の使い方が上手いな~と感じていたのでした。
使用カメラが、canonのF1だったりT90だったり・・・懐かし過ぎます。

アカショウビンの赤は森に映えます!こういう写真を見ると、長玉持って一眼で狙いたくなってしまいますね。ちょっと血が騒ぎます。

カワセミの瑠璃色は、まさに宝石です。フライフィッシングをしていると、渓流で良く出会いました。実際に見ると、この瑠璃色には感動します。釣ることを忘れて、彼の狩りを眺めていたものです。

とても懐かしい友に再会したような気持ちにさせてくれた2冊でした。
でも、懐かしい写真集が出てきました。
まだ、銀塩写真全盛の時代、カメラに夢中になっていた時期がありました。中判カメラを持ち風景写真に没頭していた頃ですね。
その頃購入した2冊の写真集。嶋田忠の「カワセミ」「炎のカムイ」どちらもカワセミ科の鳥の写真集です。嶋田忠は鳥を中心に被写体にした写真家で、NHKでも映像制作したものがあったと記憶しています。
この人の写真集は、動きがあるのと、色や光の使い方が上手いな~と感じていたのでした。
使用カメラが、canonのF1だったりT90だったり・・・懐かし過ぎます。

アカショウビンの赤は森に映えます!こういう写真を見ると、長玉持って一眼で狙いたくなってしまいますね。ちょっと血が騒ぎます。

カワセミの瑠璃色は、まさに宝石です。フライフィッシングをしていると、渓流で良く出会いました。実際に見ると、この瑠璃色には感動します。釣ることを忘れて、彼の狩りを眺めていたものです。

とても懐かしい友に再会したような気持ちにさせてくれた2冊でした。
日本人の心配り・・・ ― 2010年08月08日
たまには、毛色の違う記事をば。
JR東日本の車内販売での話。所用の帰り、宇都宮線のグリーン車の車内販売で、ビールとおつまみを購入しました。ナッツを買ったのですが、半分ほど食べ進んで指がナッツに届かなくなってきたその時!

袋の中ほどに開封用の切込みがもう1つあるのを発見しまして、それはもう感動したのです。
いや~わかってらっしゃる!

これなら、最後まで指が届くので、袋を口に付けて「ザザッ」と必要以上に流し込む事もせずに、自分のペースで食べられます。
NREの提案なのか、メーカーの提案なのか、良くぞ気付いてくれました!たった1つの切込み。もしかすると、メーカーは包材の型を作り直したりしたのかも知れないけど、こういう心配りは確実に人の心を掴みます。あっぱれ!でした。
JR東日本の車内販売での話。所用の帰り、宇都宮線のグリーン車の車内販売で、ビールとおつまみを購入しました。ナッツを買ったのですが、半分ほど食べ進んで指がナッツに届かなくなってきたその時!

袋の中ほどに開封用の切込みがもう1つあるのを発見しまして、それはもう感動したのです。
いや~わかってらっしゃる!

これなら、最後まで指が届くので、袋を口に付けて「ザザッ」と必要以上に流し込む事もせずに、自分のペースで食べられます。
NREの提案なのか、メーカーの提案なのか、良くぞ気付いてくれました!たった1つの切込み。もしかすると、メーカーは包材の型を作り直したりしたのかも知れないけど、こういう心配りは確実に人の心を掴みます。あっぱれ!でした。
今年もらっきょう漬け ― 2010年07月19日
今年も、らっきょうの甘酢漬けを仕込みました。
近所の農家から5kg分けてもらい、6時間の無になれる皮むき作業後、塩漬けしたのが2週間前。

そして今日、本漬けです。
塩漬けは、塩をらっきょうの重量の10%、酢を650㏄位、水を1350㏄位で、塩を良く溶かして漬け汁とします。1kg位のおもりをして漬け込みました。
これを、3時間ほど塩抜きをします。

この後、10秒位熱湯に浸して、冷まします。

本漬けの漬け汁を作ります。
水:400㏄位、氷砂糖と黒糖を合計で800g位、酢を400g位(総量は900g)。これを中火から弱火で沸騰しない程度に熱しながら砂糖を溶かします。

黒糖は我が家のオリジナルです。今年のらっきょうは少し甘めにしようかと思っています。それと、爽やかな酸味を出したいので、酢の半量は熱せずそのまま使用します。
良く冷めたら残りの酢(500g)を混ぜ合わせます。

熱湯にさらしたらっきょうが冷めたところでビン詰めです。予めビンはホワイトリカーで消毒しておきます。

最後に漬け汁と鷹のツメ2本を入れて蓋をします。

冷暗所に寝かせます。4ヶ月後くらいからがおいしくなり出す頃です。さて、今年のはどんな出来になるかな?
近所の農家から5kg分けてもらい、6時間の無になれる皮むき作業後、塩漬けしたのが2週間前。

そして今日、本漬けです。
塩漬けは、塩をらっきょうの重量の10%、酢を650㏄位、水を1350㏄位で、塩を良く溶かして漬け汁とします。1kg位のおもりをして漬け込みました。
これを、3時間ほど塩抜きをします。

この後、10秒位熱湯に浸して、冷まします。

本漬けの漬け汁を作ります。
水:400㏄位、氷砂糖と黒糖を合計で800g位、酢を400g位(総量は900g)。これを中火から弱火で沸騰しない程度に熱しながら砂糖を溶かします。

黒糖は我が家のオリジナルです。今年のらっきょうは少し甘めにしようかと思っています。それと、爽やかな酸味を出したいので、酢の半量は熱せずそのまま使用します。
良く冷めたら残りの酢(500g)を混ぜ合わせます。

熱湯にさらしたらっきょうが冷めたところでビン詰めです。予めビンはホワイトリカーで消毒しておきます。

最後に漬け汁と鷹のツメ2本を入れて蓋をします。

冷暗所に寝かせます。4ヶ月後くらいからがおいしくなり出す頃です。さて、今年のはどんな出来になるかな?
御礼!開設3年になりました ― 2010年07月06日
このブログを開設して、丸3年になりました。皆様、ありがとうございます。
相変わらずというより、益々超個人的、マニアックな内容になっておりますが、多くの皆さんが遊びに来ていただいており嬉しい限りです。
特に、ギターの自作ピックアップの記事をアップするようになってから、アクセスが激増しています。皆さん興味があるのですね・・・
私はというと、L.R.Baggsのアンセムに期待している状態で、すっかり半田コテを握らなくなっています(汗)
もう少し時間が経ったらアンセムに触手が伸びることでしょう・・・。
ともあれ、今後ともよろしくお願いいたします。気軽にコメントも書いてくださ~い!
相変わらずというより、益々超個人的、マニアックな内容になっておりますが、多くの皆さんが遊びに来ていただいており嬉しい限りです。
特に、ギターの自作ピックアップの記事をアップするようになってから、アクセスが激増しています。皆さん興味があるのですね・・・
私はというと、L.R.Baggsのアンセムに期待している状態で、すっかり半田コテを握らなくなっています(汗)
もう少し時間が経ったらアンセムに触手が伸びることでしょう・・・。
ともあれ、今後ともよろしくお願いいたします。気軽にコメントも書いてくださ~い!
アクセス御礼! ― 2010年03月10日
この半年、日のアクセス数がユニークユーザーで100名を超えています。本当にありがたいことです。ページに載せているカウンターはPV数です。
アクセスの多いページは、自作ピックアップに関する記事です。この関係の記事を載せ始めてからアクセス数が急増しています。
パナソニックのマイクカプセルに関するところ、圧電スピーカーの実験・・・
皆さん市販のピックアップに何らかの不満があるのでしょうかねぇ?それとも、ただ単に自作して安くあげたいとか・・・
何れにせよ、この話題の関心が高い事は確かです。
巷に、この関係の書き込みが少ないってのもあるかも知れません。でなきゃ、こんな辺境のサイトには来ないですよね(汗)
でも、このサイトにおいで下さる皆様には感謝です。これからも、いろいろ趣味の世界を拡げていきます!
今後ともよろしくお付き合いください!
アクセスの多いページは、自作ピックアップに関する記事です。この関係の記事を載せ始めてからアクセス数が急増しています。
パナソニックのマイクカプセルに関するところ、圧電スピーカーの実験・・・
皆さん市販のピックアップに何らかの不満があるのでしょうかねぇ?それとも、ただ単に自作して安くあげたいとか・・・
何れにせよ、この話題の関心が高い事は確かです。
巷に、この関係の書き込みが少ないってのもあるかも知れません。でなきゃ、こんな辺境のサイトには来ないですよね(汗)
でも、このサイトにおいで下さる皆様には感謝です。これからも、いろいろ趣味の世界を拡げていきます!
今後ともよろしくお付き合いください!
突然壊れるのが機械・・・ ― 2010年02月20日
このBlogを書いている自宅のPCが突然お亡くなりになりました。
BIOSが上がらない!HDDは動いている・・・CMOSクリアしても同じ・・・そのうちに電源が入らない・・・一瞬CPUファンが回るから電源は大丈夫かな・・・こりゃマザーが逝ったかな・・・
5年前に、AMDの初代64bit Athlon64 で3代目として作ったPC。よく働いてくれました!
仕事でも使うので早く立ち上げたいけど、近頃のx86CPUはどうなっているのか?デュアルコアになっているくらいしかわかっていない。サクッと調べたいところですが、大昔のWin98ノートでどうにか調べて、とにかく在庫のあるやつでそれなりの性能で安いやつ・・・やっぱりAMDで組みなおしました。今やメジャーな新品PCパーツは秋葉原辺りの店頭で買うよりネットの方が安いのです。ダウンしたその日のうちにオーダーです。
CPUはAMD Phenom™ II X2 550 \8500位。クロック3.1GHzとトータルキャッシュが7MB。2コア。クロック周波数が3GHzの時代に入って、発熱と消費電力の増大に対応するために、近頃のCPUはデュアルコアになっています。クロックは上げずに仕事を分担させて同時に処理して、結果、性能を向上させるというもの・・・昔はCPUそのものを複数搭載していたものです。Phenom™ II は4コア搭載モデルまであります。

マザーは、GIGABYTEのMA785GT-UD3H。\11000位
あとはメモリーを買って・・・。

2日のダウンで復活の巻でした。これまでも決して遅くなかったですが、更に快適になりました。特にネットは確実に速くなってますねぇ。
BIOSが上がらない!HDDは動いている・・・CMOSクリアしても同じ・・・そのうちに電源が入らない・・・一瞬CPUファンが回るから電源は大丈夫かな・・・こりゃマザーが逝ったかな・・・
5年前に、AMDの初代64bit Athlon64 で3代目として作ったPC。よく働いてくれました!
仕事でも使うので早く立ち上げたいけど、近頃のx86CPUはどうなっているのか?デュアルコアになっているくらいしかわかっていない。サクッと調べたいところですが、大昔のWin98ノートでどうにか調べて、とにかく在庫のあるやつでそれなりの性能で安いやつ・・・やっぱりAMDで組みなおしました。今やメジャーな新品PCパーツは秋葉原辺りの店頭で買うよりネットの方が安いのです。ダウンしたその日のうちにオーダーです。
CPUはAMD Phenom™ II X2 550 \8500位。クロック3.1GHzとトータルキャッシュが7MB。2コア。クロック周波数が3GHzの時代に入って、発熱と消費電力の増大に対応するために、近頃のCPUはデュアルコアになっています。クロックは上げずに仕事を分担させて同時に処理して、結果、性能を向上させるというもの・・・昔はCPUそのものを複数搭載していたものです。Phenom™ II は4コア搭載モデルまであります。

マザーは、GIGABYTEのMA785GT-UD3H。\11000位
あとはメモリーを買って・・・。

2日のダウンで復活の巻でした。これまでも決して遅くなかったですが、更に快適になりました。特にネットは確実に速くなってますねぇ。
楽器フェア2009 ― 2009年11月08日
2年に一度開催の楽器フェアに行って来ました。パシフィコ横浜。
大きな目的は2つ。ヤイリギターを覗くことと、復活したRhodesPianoを体感すること。
中華街で昼食を摂った後会場へ。
出展者は予め確認してましたが、少ないですな・・・不況は影響しているようです。打楽器系が少ないのが、元々ドラマーの私にとっては寂しい限り・・・。ヤマハのブースも何だか元気無かったし。
そんな中、ヤイリさんはアコギブースでは一番の元気良さ!さすがですよ。

このバリエーションの多彩さは、他社には見られないものです。道前さんが受付してました。マスクして・・・
差し入れをお渡しして、ひとまずサクっと見させてもらいました。

CustomShop製。リラが異彩を放ってます。真ん中の象牙を使ったサファリギター?勝手に呼んでますが・・・。指板のインレイがジャングル大帝です(笑)。完成前の状態を小池さんに見せていただきましたが、非常に細かいインレイです。貝だけでなく、石系も使っているそうです。
そして、一番右が道前さんのハカ。人が多かったし、会場全体がうるさいので試奏しませんでした。またヤイリにお邪魔した時にゆっくり弾かせてもらいます。

この島の裏に回ると、丹羽さんの作品が並んでます。木工の精細さは相変わらず綺麗です。フィンガースタイルを意識したモデルだと思います。モデル名が「NF-Madagascar」。NFってボディはヤイリにありましたっけ?新しいボディシェイプかもしれません。サイド/バックはマダガスカルローズウッドでしょうかねぇ。あの、ハカと似た?杢の。
私好みのデザインとしては、ポジションは無しで、ブリッジとかにある☆はいらないかな・・・

このギター。サドルが独立してます。こちらも試奏しませんでしたが、各弦の分離が良いのでしょうか?これも、静かな所で試したいですね。ヤイリで是非弾かせていただきたい!ラベルがCustomShop向けなのかな?新しいデザインになってました。
小池さんとも再会できて、ご挨拶がてら雑談させていただきました。あのような雑踏?の中ですと何だか落ち着かないですね。やっぱり、ヤイリの工房でゆっくりお話するのが良いです!
さて、もうひとつの目的。25年ぶりに復活した、RhodesPiano(ローズピアノ)!
RhodesPianoについては、Wikiなどで調べていただくことにして・・・
私がキーボードに興味が沸いたきっかけが、このRhodesPianoの音色だったのです。
Rhodesは、1987年にRolandがその商標権を獲得して、Rhodes Mark60や80はデジタル音源となって、往年のオリジナルRhodesではなくなってしまいました。確かに良くサンプリングされてはいたものの、打鍵によって微妙に変化するアタック音や歪み具合は再現しきれていませんでしたねぇ。内部の錆び具合や調整で個体差が微妙にあるものなので当たり前ですが・・・。
1997年にRhodes社が再び商標権を獲得して、現在に至ります。そして、80年代前半までに採用されていた音源機構を再現して、プリアンプの改良やMIDI対応などもプラスした3モデルを、Mark7として復活したのです。日本は今年の9月から販売開始しています。



内部をこんな間近で見たのは始めてでした。音叉のようなものを打撃して音を出すのです。強く打鍵すると、あの金属的なアタックが聴かれるのも、ロングトーンであるのも、あのコロコロした高音も、この音源機構だから出るのです。
そして、トレモロパン機能によって、ステレオで左右に振られる感じは、もう、リチャード・ティーになりきれます。
MK1ほどではないけど、深く打たないと鳴らないキーボードタッチは健在だし、これまで楽器屋でたま~に置いてある、ボロボロのスーツケースを弾かせてもらって、いいなぁ~と思っていましたが、ピカピカのMark7を弾かせてもらって「これを待っていたミュージシャンは多かろう」と思いました。
オルガンタッチに慣れた人には鳴らしにくいピアノかもしれません。でも、サンプリング音源とは明らかに違う。
実際に、ジョー・サンプルはツアーで使い出すようですね。ごもっとも!
Rhodes社のオフィシャルページ。
そんな楽器フェア2009でした。全体的には元気なかったなぁ~
あぁ、川上ギターも出展してました。弾きませんでしたが。
大きな目的は2つ。ヤイリギターを覗くことと、復活したRhodesPianoを体感すること。
中華街で昼食を摂った後会場へ。
出展者は予め確認してましたが、少ないですな・・・不況は影響しているようです。打楽器系が少ないのが、元々ドラマーの私にとっては寂しい限り・・・。ヤマハのブースも何だか元気無かったし。
そんな中、ヤイリさんはアコギブースでは一番の元気良さ!さすがですよ。

このバリエーションの多彩さは、他社には見られないものです。道前さんが受付してました。マスクして・・・
差し入れをお渡しして、ひとまずサクっと見させてもらいました。

CustomShop製。リラが異彩を放ってます。真ん中の象牙を使ったサファリギター?勝手に呼んでますが・・・。指板のインレイがジャングル大帝です(笑)。完成前の状態を小池さんに見せていただきましたが、非常に細かいインレイです。貝だけでなく、石系も使っているそうです。
そして、一番右が道前さんのハカ。人が多かったし、会場全体がうるさいので試奏しませんでした。またヤイリにお邪魔した時にゆっくり弾かせてもらいます。

この島の裏に回ると、丹羽さんの作品が並んでます。木工の精細さは相変わらず綺麗です。フィンガースタイルを意識したモデルだと思います。モデル名が「NF-Madagascar」。NFってボディはヤイリにありましたっけ?新しいボディシェイプかもしれません。サイド/バックはマダガスカルローズウッドでしょうかねぇ。あの、ハカと似た?杢の。
私好みのデザインとしては、ポジションは無しで、ブリッジとかにある☆はいらないかな・・・

このギター。サドルが独立してます。こちらも試奏しませんでしたが、各弦の分離が良いのでしょうか?これも、静かな所で試したいですね。ヤイリで是非弾かせていただきたい!ラベルがCustomShop向けなのかな?新しいデザインになってました。
小池さんとも再会できて、ご挨拶がてら雑談させていただきました。あのような雑踏?の中ですと何だか落ち着かないですね。やっぱり、ヤイリの工房でゆっくりお話するのが良いです!
さて、もうひとつの目的。25年ぶりに復活した、RhodesPiano(ローズピアノ)!
RhodesPianoについては、Wikiなどで調べていただくことにして・・・
私がキーボードに興味が沸いたきっかけが、このRhodesPianoの音色だったのです。
Rhodesは、1987年にRolandがその商標権を獲得して、Rhodes Mark60や80はデジタル音源となって、往年のオリジナルRhodesではなくなってしまいました。確かに良くサンプリングされてはいたものの、打鍵によって微妙に変化するアタック音や歪み具合は再現しきれていませんでしたねぇ。内部の錆び具合や調整で個体差が微妙にあるものなので当たり前ですが・・・。
1997年にRhodes社が再び商標権を獲得して、現在に至ります。そして、80年代前半までに採用されていた音源機構を再現して、プリアンプの改良やMIDI対応などもプラスした3モデルを、Mark7として復活したのです。日本は今年の9月から販売開始しています。



内部をこんな間近で見たのは始めてでした。音叉のようなものを打撃して音を出すのです。強く打鍵すると、あの金属的なアタックが聴かれるのも、ロングトーンであるのも、あのコロコロした高音も、この音源機構だから出るのです。
そして、トレモロパン機能によって、ステレオで左右に振られる感じは、もう、リチャード・ティーになりきれます。
MK1ほどではないけど、深く打たないと鳴らないキーボードタッチは健在だし、これまで楽器屋でたま~に置いてある、ボロボロのスーツケースを弾かせてもらって、いいなぁ~と思っていましたが、ピカピカのMark7を弾かせてもらって「これを待っていたミュージシャンは多かろう」と思いました。
オルガンタッチに慣れた人には鳴らしにくいピアノかもしれません。でも、サンプリング音源とは明らかに違う。
実際に、ジョー・サンプルはツアーで使い出すようですね。ごもっとも!
Rhodes社のオフィシャルページ。
そんな楽器フェア2009でした。全体的には元気なかったなぁ~
あぁ、川上ギターも出展してました。弾きませんでしたが。
ねこまんま... ― 2009年10月27日
どうでも良いのかもしれませんが・・・(汗)
私のハンドル(って言い方がパソ通時代?)が「ねこまんま」です。もう20年以上この名前で通してますが、まぁ、響きが良いのと、食べ物の「ねこまんま」が好きだってのが理由です。
で。「ねこまんま」って、私の中では、熱々ご飯にかつを節に醤油。アクセントに時にはゴマ・・・。あ~食いたくなってきた!新米の時期だし!
これを唯一無二の「ねこまんま」だと信じてこれまで生きてきたのですが、どうも、「ねこまんま」レシピ本なぞちょっと前に出たりして、それには火を使わず、単純工程でオン・ザ・ライス!ってのが満載・・・。
妻はみそ汁ぶっかけご飯が「ねこまんま」だと言うし・・・
う~む。「ねこまんま」はかつを節ご飯だ!
そんな・・・猫はいろいろ食わんぞ!
と、私、「ねこまんま」は吠えるのでした。
皆さんの食べ物のねこまんまのイメージって、どんなでしょう?
私のハンドル(って言い方がパソ通時代?)が「ねこまんま」です。もう20年以上この名前で通してますが、まぁ、響きが良いのと、食べ物の「ねこまんま」が好きだってのが理由です。
で。「ねこまんま」って、私の中では、熱々ご飯にかつを節に醤油。アクセントに時にはゴマ・・・。あ~食いたくなってきた!新米の時期だし!
これを唯一無二の「ねこまんま」だと信じてこれまで生きてきたのですが、どうも、「ねこまんま」レシピ本なぞちょっと前に出たりして、それには火を使わず、単純工程でオン・ザ・ライス!ってのが満載・・・。
妻はみそ汁ぶっかけご飯が「ねこまんま」だと言うし・・・
う~む。「ねこまんま」はかつを節ご飯だ!
そんな・・・猫はいろいろ食わんぞ!
と、私、「ねこまんま」は吠えるのでした。
皆さんの食べ物のねこまんまのイメージって、どんなでしょう?
三升漬に挑戦! ― 2009年08月08日
札幌出張でした。
行きつけの居酒屋に行くと、冷やっこの上に黒いちょっとトロみの付いたペースト状のソースというか・・・乗って出てきました。 これがピリっと辛くて大変おいしい。冷やっこと合う!醤油味だけど深い味わい・・・。
「これ何?」とおかみに聞くと。
「三升漬(さんじょうづけ)だよ。」
「さんじょうづけって、すぐそこ南三条だからかい?」って素朴に・・・
「何言ってんの!お酒や醤油で使う単位の三升だよ」っておかみ。
「なるほど。旨いね。はじめてだよ。」って私。
で、いつものコースで「Bar Chot」へ。
お店の大きい方のマスコット(^_^;ハルちゃん登場!
「ねこさん(本当は本名ね)南蛮買って来たんだよね。」
「何作るのさ?」って私。
「あの、黒い・・・」って、ハルちゃん。名前が出てこない・・・
(ハルちゃん。名詞が出てこないのはしゃ~ないけどね。ちょっと多すぎよ!)
「三升漬かい?」って私。
「そうそう!」
私も、ついさっき体験したばかりの三升漬け。偶然とは恐ろしいもので、そのノリでレシピをネットで調べ始め、遂には二人でそれぞれ作ることになりました。
早速、最終日に南蛮(青唐辛子)を購入して、帰途に着いたのです。
三升漬けに関しては、ネットで調べてみてくださいね。
さて作り方。大変簡単です。
青唐辛子と醤油と米麹を一升づつ混ぜるだけだから、三升漬けともいわれているそうですね。実際には、それを1~2ヶ月寝かせる。中には3年ものってのもあるそう・・・。
手順は、南蛮を刻んで混ぜて寝かせる!以上!
今回の南蛮は北海道は栗山で獲れたもの。これで3袋分約550g。辛い南蛮でなくてはなりません。

そして、醤油、麹

味を良くする昆布。これは、ハルちゃんからいただきました!ありがと!乾燥したものです。5mm程度にはさみでチョキチョキしました。

南蛮は、水洗いし水気を良く切って、3mm程度の小口切りにします。ひたすらザクザク切ります。ハルちゃんみたく、辛くなった指を娘のあさよちゃんになめさせて、悶絶させる意地悪ばあさんにはなりたくないものです・・・人間として(^_^;
約500gになりました。

結構な量になったので、大きめの鍋で全ての材料をよく混ぜました。
麹は400g。醤油は材料がひたひたになるくらい。

2リットルの漬物ビンを用意し、消毒しておきます。耐熱対応ではないので、ホワイトリカーで内部を殺菌しました。
そして投入しました。何とか入りました。
でも、これって切り返し必要?できないじゃない・・・

麹の発酵が収まる2週間目位から食べられるようですが、この状態で2ヶ月位は置きたいですね。
冷暗所での寝かせと言うことですが、酷暑の時は冷蔵庫に入れましょう。あとは、カビ類の発生が心配ですね。こまめにチェックが必要です。管理は味噌を作るのと似てるかもしれません。

で、ハルちゃん。既に味見始めてるって聞いたけど、2ヵ月後には無くなっちゃうでしょう!味比べするんだから残しておいてよ!
行きつけの居酒屋に行くと、冷やっこの上に黒いちょっとトロみの付いたペースト状のソースというか・・・乗って出てきました。 これがピリっと辛くて大変おいしい。冷やっこと合う!醤油味だけど深い味わい・・・。
「これ何?」とおかみに聞くと。
「三升漬(さんじょうづけ)だよ。」
「さんじょうづけって、すぐそこ南三条だからかい?」って素朴に・・・
「何言ってんの!お酒や醤油で使う単位の三升だよ」っておかみ。
「なるほど。旨いね。はじめてだよ。」って私。
で、いつものコースで「Bar Chot」へ。
お店の大きい方のマスコット(^_^;ハルちゃん登場!
「ねこさん(本当は本名ね)南蛮買って来たんだよね。」
「何作るのさ?」って私。
「あの、黒い・・・」って、ハルちゃん。名前が出てこない・・・
(ハルちゃん。名詞が出てこないのはしゃ~ないけどね。ちょっと多すぎよ!)
「三升漬かい?」って私。
「そうそう!」
私も、ついさっき体験したばかりの三升漬け。偶然とは恐ろしいもので、そのノリでレシピをネットで調べ始め、遂には二人でそれぞれ作ることになりました。
早速、最終日に南蛮(青唐辛子)を購入して、帰途に着いたのです。
三升漬けに関しては、ネットで調べてみてくださいね。
さて作り方。大変簡単です。
青唐辛子と醤油と米麹を一升づつ混ぜるだけだから、三升漬けともいわれているそうですね。実際には、それを1~2ヶ月寝かせる。中には3年ものってのもあるそう・・・。
手順は、南蛮を刻んで混ぜて寝かせる!以上!
今回の南蛮は北海道は栗山で獲れたもの。これで3袋分約550g。辛い南蛮でなくてはなりません。

そして、醤油、麹

味を良くする昆布。これは、ハルちゃんからいただきました!ありがと!乾燥したものです。5mm程度にはさみでチョキチョキしました。

南蛮は、水洗いし水気を良く切って、3mm程度の小口切りにします。ひたすらザクザク切ります。ハルちゃんみたく、辛くなった指を娘のあさよちゃんになめさせて、悶絶させる意地悪ばあさんにはなりたくないものです・・・人間として(^_^;
約500gになりました。

結構な量になったので、大きめの鍋で全ての材料をよく混ぜました。
麹は400g。醤油は材料がひたひたになるくらい。

2リットルの漬物ビンを用意し、消毒しておきます。耐熱対応ではないので、ホワイトリカーで内部を殺菌しました。
そして投入しました。何とか入りました。
でも、これって切り返し必要?できないじゃない・・・

麹の発酵が収まる2週間目位から食べられるようですが、この状態で2ヶ月位は置きたいですね。
冷暗所での寝かせと言うことですが、酷暑の時は冷蔵庫に入れましょう。あとは、カビ類の発生が心配ですね。こまめにチェックが必要です。管理は味噌を作るのと似てるかもしれません。

で、ハルちゃん。既に味見始めてるって聞いたけど、2ヵ月後には無くなっちゃうでしょう!味比べするんだから残しておいてよ!
ブログ内検索:
Loading

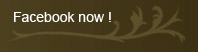

最近のコメント