ギターの響き ― 2008年03月16日
アコースティックギターは、弦の振動がサドル~ブリッジに伝わり、いち早く表板が共鳴し、側板から裏板へと伝わり、胴内の空気も共鳴しサウンドホールから音が出ますよね。更に共鳴した胴内の空気によりまた表板も振動し裏板へと・・・その繰り返しがサスティンということになると思います。
 音を出すために、まず弦の振動を胴全体に響かせなくてはならない表板は、非常に重要になります。ですから音の伝達速度が速い材(スプルースやセダーなど)で作られているわけです。
音を出すために、まず弦の振動を胴全体に響かせなくてはならない表板は、非常に重要になります。ですから音の伝達速度が速い材(スプルースやセダーなど)で作られているわけです。
試しに開放の5弦と4弦を同時に強めに弾いて表板のいろいろな部分に手を押し付けてみてください。ブリッジの直ぐ下。ピックガード・・・・。意外とハッキリ音の変化を感じることができると思います。表板の振動は大切なんです。できればピックガードは外したい気分になります。
では、側板や裏板はどのような役割があるのか?たまたま、私はドラムをやっているので、これの構造と同じだと理解しています。
ドラムの胴は空洞のパイプみたいな形になっていて、メイプルなどの堅い木が使われており、厚さも1cmから3cm位あるものもあり、その多くは数層からなる合板です。これの両端に皮が張られています。胴自体が激しく振動し周囲の空気を振動させるというものではなく、トップ(表皮)の振動を胴内の反射も含めて、なるべくロスなく且つ高速にボトム(裏皮)に伝える役割です。
タム(ドラムセットでいっぱい並んでいる太鼓)のチューニングでは、トップは主に音程(ピッチダウン効果も含めて)の決定を行ないます。ボトムは、皮の張りによってサスティンや音程の微調整を行ないます。また、胴の長さはサスティンの長さや音量に関係してきます。長ければサスティンも長く、音量も大きい。また、口径が小さければ高い音が、大きければ低い音になります。タムのチューニングでは欲しい音程やサスティンの長さを、トップ/ボトムの張りを調節して作っていきます。皮は必ずしも均一に張るものではなく、一部を少し緩めて響き方や不快な倍音?を抑えるテクニックがあります。ティッシュ等を畳んでガムテープで貼りミュートしても同様の効果があります。要は美しく共鳴するおいしい所の振動だけにフィルタリングするようなものだと思います。アコギでいうところのブレイス(力木、響棒)はこれに当たると思いますが、どうでしょう・・・。
ドラムの音の伝達をアコースティックギターに置き換えれば、側板は裏板へ表板の振動を伝える役割を、裏板はサスティンや音質に関係してくるという事になりますかねぇ。まさに、トーンウッドと呼ばれるゆえんです。ボディサイズも大きければ音量は大きいしサスティンも長い。裏板に比重の重いローズウッドが使われるのは、響きを持続する時間がスプルースより長いためとされています。また、マホガニーはローズより比重が軽く、響きの持続時間も短いため、マホのギターは「カラッとした音だ」というようなことが言われる訳です。
ただ、音質という面では、こういったものだけでは片付けられない更に複雑な要素が関係すると思います。ブレイスによる表板の響き方から始まり、ボディの厚さ、材の板厚、弦の種類などなど・・・。この無数の組み合わせにより、ギター毎に違った音が聞き分けられます。そこに面白さや奥深さを感じ、ギターの魅力の一つになっているんでしょうね。
 音を出すために、まず弦の振動を胴全体に響かせなくてはならない表板は、非常に重要になります。ですから音の伝達速度が速い材(スプルースやセダーなど)で作られているわけです。
音を出すために、まず弦の振動を胴全体に響かせなくてはならない表板は、非常に重要になります。ですから音の伝達速度が速い材(スプルースやセダーなど)で作られているわけです。試しに開放の5弦と4弦を同時に強めに弾いて表板のいろいろな部分に手を押し付けてみてください。ブリッジの直ぐ下。ピックガード・・・・。意外とハッキリ音の変化を感じることができると思います。表板の振動は大切なんです。できればピックガードは外したい気分になります。
では、側板や裏板はどのような役割があるのか?たまたま、私はドラムをやっているので、これの構造と同じだと理解しています。
ドラムの胴は空洞のパイプみたいな形になっていて、メイプルなどの堅い木が使われており、厚さも1cmから3cm位あるものもあり、その多くは数層からなる合板です。これの両端に皮が張られています。胴自体が激しく振動し周囲の空気を振動させるというものではなく、トップ(表皮)の振動を胴内の反射も含めて、なるべくロスなく且つ高速にボトム(裏皮)に伝える役割です。
タム(ドラムセットでいっぱい並んでいる太鼓)のチューニングでは、トップは主に音程(ピッチダウン効果も含めて)の決定を行ないます。ボトムは、皮の張りによってサスティンや音程の微調整を行ないます。また、胴の長さはサスティンの長さや音量に関係してきます。長ければサスティンも長く、音量も大きい。また、口径が小さければ高い音が、大きければ低い音になります。タムのチューニングでは欲しい音程やサスティンの長さを、トップ/ボトムの張りを調節して作っていきます。皮は必ずしも均一に張るものではなく、一部を少し緩めて響き方や不快な倍音?を抑えるテクニックがあります。ティッシュ等を畳んでガムテープで貼りミュートしても同様の効果があります。要は美しく共鳴するおいしい所の振動だけにフィルタリングするようなものだと思います。アコギでいうところのブレイス(力木、響棒)はこれに当たると思いますが、どうでしょう・・・。
ドラムの音の伝達をアコースティックギターに置き換えれば、側板は裏板へ表板の振動を伝える役割を、裏板はサスティンや音質に関係してくるという事になりますかねぇ。まさに、トーンウッドと呼ばれるゆえんです。ボディサイズも大きければ音量は大きいしサスティンも長い。裏板に比重の重いローズウッドが使われるのは、響きを持続する時間がスプルースより長いためとされています。また、マホガニーはローズより比重が軽く、響きの持続時間も短いため、マホのギターは「カラッとした音だ」というようなことが言われる訳です。
ただ、音質という面では、こういったものだけでは片付けられない更に複雑な要素が関係すると思います。ブレイスによる表板の響き方から始まり、ボディの厚さ、材の板厚、弦の種類などなど・・・。この無数の組み合わせにより、ギター毎に違った音が聞き分けられます。そこに面白さや奥深さを感じ、ギターの魅力の一つになっているんでしょうね。
ブログ内検索:
Loading

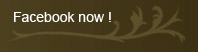

最近のコメント